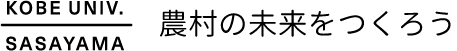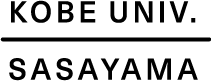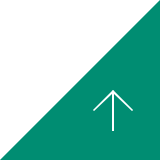【2011実践農学入門】ボランティア活動③
2011年11月20日(日)「みたけの里秋の収穫感謝祭」-篠山市畑地区
神戸大からは17名の学生がボランティアとして畑地区を訪れ、当祭りのお手伝いをさせていただきました。
収穫祭は開会式を経て、もちつき、野菜の品評会、猪汁やお弁当ののふるまい、そして野菜の直売会など、多くのお客様でにぎわっていました。
実習を通して行うボランティア活動のよい点として、おもに3つがあげられるように思います。
・・・・①農家さんとのコミュニケーション能力の向上・・・・
17名のうち6名は金曜日から畑地区にお世話になり、収穫祭の準備をしていたようです。
自分たちで連絡をとり、農家さんのおうちに宿泊。
実習が始まったころにはまったくできなかったことです。
農家と学生とが独自に関係をもってくれることが、この実習の目的の一つでもあります。
このまま、実習が終わっても畑地区にくるようになってくれれば、大成功です。
・・・・②とにかく手を動かせる人に・・・・
もちつきのときのエピソードを紹介します。
地元の方に「はいっ、じゃあもちつきしてみて!」と杵を手渡された学生ら。
当然、もちつきなどほとんど経験したことのない学生たちは、不安そうに杵をもち、蒸されたもち米をつき始めました。
いざ、手水とともにもちをつく時間に。
「ペチッ」
あれー、全然腰が入ってない。
「餅もつけんのかー、しゃーないなぁ。ちょっと交代」
そして、地元の方に登場してもらいます。
「バチッ」
「おーーーー」
全然、杵でもちをつく音が違うんですね。
学生たちは、「つきかたがわからないから教えてください」というよりも前に、「いいからついてみろ」といって、杵を渡されていました。この、「実際にやってみる」までのタイミングが早いのが、農村でお世話になる醍醐味だと思います。座学、実践、実社会と、学生たちが頭の知識と経験とをリンクさせて社会で活動するようになるまでには、だいぶ時間がかかります。
つべこべいわずに手を動かすことを求められて、学生たちは知識と経験とをリンクすることができるわけです。大事な4年間のなかで、少しでもこういった経験を積んでほしいなぁと思います。
・・・・③学生同士のコミュニケーション・・・・
実習では、いつも同じメンバーで構成する班に分かれて活動しているので、案外ほかにどんな学生がいるのかを知りません。ボランティア活動を通して、異なる班のメンバーと活動し、共通の趣味や考え方などを意見交換していました。いろいろな動機でこの授業に参加する学生たちの間で共通しているのが「篠山へいくこと」です。同様な趣味をもった学生とこの実習で出会うことになるかもしれません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とにかく、畑地区のみなさんにはいつも温かく迎えていただき、ほんとうに感謝しています。
また、12月にお会いできる日を楽しみにしています。
(布施未恵子)